 巣作り中の エナガ 2016年3月22日15時17分 長野県 安曇野市 |
私の雑記帳 風と光と鳥たちと思いつくまま、気の向くまま、今日もふらふらと駄文が続きます。
なお、駄文は3年ほどで消すことにしています。あまり、だらだらと続くのも芸がないと思いますので。
Copyright (C) 2002-2016 Nobuyuki Ota All Rights Reserved
3月22日 エナガの巣作り
 巣作り中の エナガ 2016年3月22日15時17分 長野県 安曇野市 |
昨日のエナガ 2016年3月21日14時56分 |
昨日巣作りを始めたエナガを見に行った。ほぼ24時間後に。巣は半分ほど出来上がっていた、驚く速さ。夜間は作業をしないだろうから、ほぼ半日でこれだけ作り上げた。ただ、ただ、感激、感歎。 巣材を探し回る範囲は、巣からせいぜい200mほど。それより遠出すると、隣の番と衝突することになる。さして広くない範囲で、この量の巣材を探し出せるのだから凄い能力である。 特に繊維(白い部分)をよくもこれだけ集められると感心する。何かの繭を集めて来るのだろうが。林内を歩いても、繭は人間の目に止まらないない場所にある。樹皮の裏だったり、樹の裂け目の中だったり。ちっちゃな眼だけれど、とてもよく見えるのだろう。 この巣が、壊されず、無事に雛が誕生するよう願うばかり。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しばらく、雑記をお休みします。たぶん4月5日過ぎには再開出来ると思います。 |
 巣作り中の エナガ 2016年3月22日 長野県 安曇野市 |
 巣作り中の エナガ 2016年3月22日 長野県 安曇野市 |
3月21日 悲しい現実
 ヤナギの花を食べる ヒヨドリ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |
|
 ヤナギの花を食べる ヒヨドリ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 ヤナギの花を食べる ベニマシコ ♀ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |
|
 ヤナギの花を食べる ベニマシコ ♂ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |
|
 ヤナギの若芽を食べる ベニマシコ ♂ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |
|
 壊されたエナガの巣 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 完成しているエナガの巣 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |
|
 巣作りを始めたばかりの エナガ 2016年3月21日 長野県 安曇野市 |
3月19日 ヒナがいた
 アオサギ ヒナ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |
|
|
3月18日 今日のややこし君
 オオダイサギ 2016年3月18日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 オナガガモ 雄化した♀? 2016年3月18日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 オナガガモ 奥から ♂ 雄化した♀ ♀ |
|
 |
|
 |
|
 |
3月17日 コロニーは大賑わい
 アオサギのコロニー 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 抱卵中のアオサギ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |
|
 巣作り中のアオサギ番 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 アオサギ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |
|
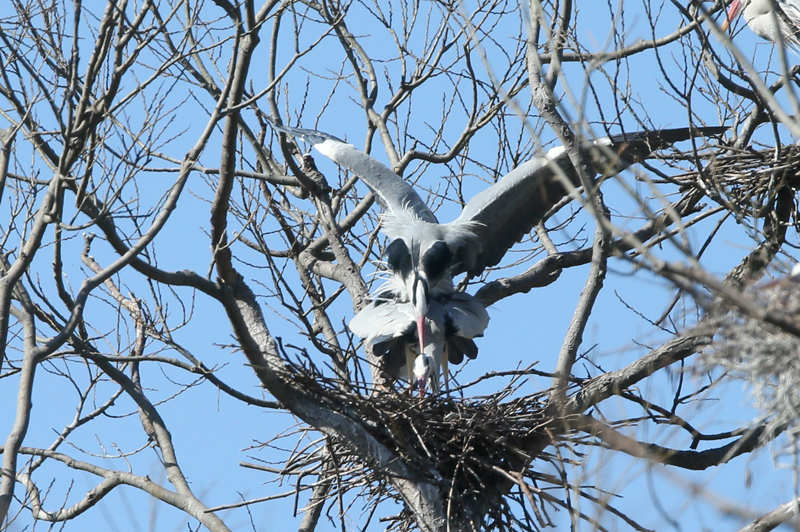 交尾中のアオサギ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 交尾中のアオサギ 2016年3月17日 長野県 安曇野市 |
3月12日 風を
 コハクチョウ 2016年3月12日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 ベニマシコ ♂ 2016年3月12日 長野県 安曇野市 |
|
 ベニマシコ ♂ 2016年3月12日 長野県 安曇野市 |
3月11日 行きつ戻りつ冬が行く
 ニワトコ 2016年3月11日 長野県 松本市 |
|
|
|
 ルリビタキ ♀ 2016年3月11日 長野県 松本野市 |
|
|
|
 ノスリ 2016年3月11日 長野県 安曇野市 |
3月10日 まだまだ冬枯れ
 オオタカの番 左が♀ 2016年3月10日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 カシラダカ ♀ 2016年3月10日 長野県 安曇野市 |
3月9日 オオムシクイのこと
 特急 しなの 2016年3月9日 長野県 松本市 |
 庭のクロッカス 2016年3月9日 長野県 松本市 |
 庭の梅 2016年3月9日 長野県 松本市 |
 庭の梅 2016年3月9日 長野県 松本市 |
昨日の最高気温22度が絵空事みたいな雪降り。始めは雨に雪が交じるくらいかと思ったが、見る間に積もって、冬に逆戻り。昨日飛び回っていた蝶も雪に埋もれているのだろうか。 こんな日は、さすがに出かける気分になれず、久しぶりに古い画像と記録の整理に手を着ける。雪とまるで関係ない話だが、フォルダー「??」に入れてある鳥に決着を付ける。 06年10月の戸隠で撮ったムシクイ、当時の雑記にはメボソムシクイと書いてある。こんなに遅くまでメボソがいるのか??だったが。 09年10月、安曇野のフィールドで数羽の群れを見かけ、渡り途中のメボソと雑記した。やはり、今頃メボソの集団がいるのだろうかと思いつつ。 当時、ムシクイの分類はメボソムシクイ、コメボソムシクイ、センダイムシクイなどとされていた。 センダイとメボソはたくさんいたし、春秋の渡りの時季にもそこそこの数がフィールドを通過した。 しかし、ずっとコメボソと確信を持てるムシクイとは出会えなかった。 |
 オオムシクイ 2006年10月13日 長野県 戸隠 |
|
|
|
 オオムシクイ 2009年10月01日 長野県 安曇野市 |
3月8日 最高気温が
 スジボソヤマキチョウ ♀ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 産卵中のスジボソヤマキチョウ ♀ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 エナガ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 エナガ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 アオサギ 2016年3月8日 長野県 安曇野市 |
3月5日 平凡な鳥見
 マガモ♀とペアの「マルガモ」 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 マガモ♀とペアの「マルガモ」 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |
|
 マガモ♀とペアの「マルガモ」 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 スズガモ ♂ 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 ハシボソガラス 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |
|
 ハシボソガラス 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |
|
 ハシボソガラス と 作りかけの巣 2016年3月5日 長野県 安曇野市 |
3月2日 イカルチドリのこと
 イカルチドリ 2016年3月2日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 イカルチドリ 尾羽を開いている方が♂ 2014年4月1日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 イカルチドリ 左♀ 右♂ 2014年4月1日 長野県 安曇野市 |
|
 爆走する オオバン 2016年3月2日 長野県 安曇野市 |
|
 爆走する オオバン 2016年3月2日 長野県 安曇野市 |
3月1日 雑木林は
 アトリ ♀ 2016年3月1日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 巣作り中の エナガ 2016年3月1日 長野県 安曇野市 |
|
|
|
 オオタカ ♀ 2016年3月1日 長野県 安曇野市 |